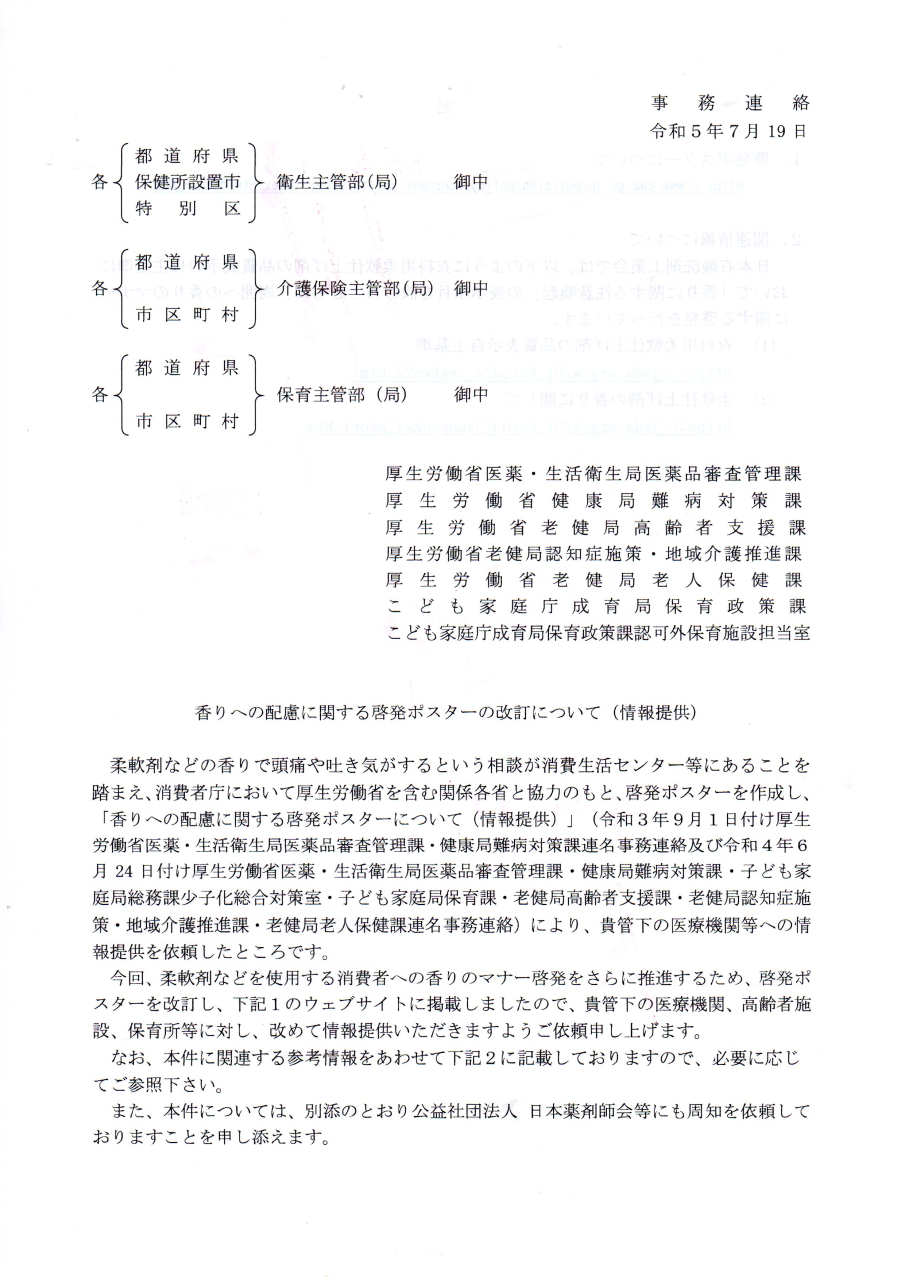山下ふみこオフィシャルブログ
香害
2025.07.19
香害及び化学物質過敏症への対応 by 6月議会
2000 年代後半から強い香りの柔軟剤が輸入 され始め、その後、人工香料の国内生産量も倍増、日本では、香りの害という
香害、長期的に見れ ば、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、がん、アルツハイマーなど、様々な健康被害を及ぼすと指摘さ れ始めている。2017 年には日本消費者連盟が香害 110 番という相談窓口を開設してからは、香 りによる害が社会問題として、認知されてきている。まず、香害や化学物質過敏症によって、教 育現場はもちろん、市役所、図書館、公民館などの公共施設において、利用者や働く人が困っている状況がある。
Q:公共施設の利用に困難を抱えている方々への認識や対応について
A教育次長:学校施設の利用に困難を抱えている児童生徒は柔軟剤等の香りが人によっては不快に感じ、頭痛等の症状を引き起こす場合がある ことは承知している。
・児童生徒の実態把握は、毎年、保護者には、保健調査票の作 成記入をお願いしており、様々なアレルギー疾患等について報告させている。(これまで1件もない?)香害及び 化学物質過敏症についての項目はないが、自由記載欄にて記入し、学校生活を送るための資料としている。
柔軟剤等の香りが苦手 であるなどの申出があれば、例えば、給食着の洗濯時に保護者に柔軟剤の使用制限等のお願 いをするなど、できる範囲で個別に対応する。
A市民福祉部長:香害及び化学物質過敏症によ り公共施設の利用に困難を抱えている方々への認識について、合成香料や化学物質 の安全性、危険性について、現時点では十分に解明されていないことから、抜本的な対策を講じる ことが困難な状況である。
Q:児童生徒、市民の相談などの実態と対応について
その症状には頭痛、吐き気動機倦怠感など、人によって様々で、その症状が香りに含まれる化学 物質が原因となっていること自体、気づきにくく、周囲の理解が得られず苦しんでいるケ ースもある。
対応の事例として、宝塚市教育委員会は、児童生徒の実態を知るた め、全保護者にアンケート調査を行い、その結果を受けて、保護者に配慮を求める対応をとってい る。また、小中学校、幼稚園等が把握するため、保護者が提出する保健調査票に化学物質過敏症 の有無を記入できるようにしている。
A市民福祉部長:香害や化学物質過敏症が疑われる 症状が発生しても、他の疾患が原因である場合もあり、その実態把握は非常に困難で、本市におい て把握できていない。
香害等に関連する本市への相談等につきましては、令和6年度 以降で、香害について周知すべきであるとの意見が1件、化学物質過敏症に関する生活上の相談が 1件で合計2件あり、それぞれ個別に対応したものである。(対応した?)
市民への周知は、本市の公共施設において香りへの配慮を呼びかける啓発ポ スターの掲示や、香害、化学物質過敏症に関する情報のホームページへの掲載を行うとともに、本 市職員に対し配慮を呼びかけるなど、周知に努める。
Q:周知と健康被害の予防等に向けた取組みについて
香害や化学物質過敏症のものだけが予防に向けた取組は不可能。直接の加害者は、香害への 認識を持たないまま、悪意なく、ただ普通の商品として使用している私たちなのです。自分が日常 的に使っている化学物質が、誰かを苦しめていることをまず知ること。
そして自分もまたいつ その被害者になるのか分からないわけで、知ることで、行動は変わる。化学物質過敏症とはど ういうものか、何が原因になっているのか、どういう配慮が必要なのか、ホームページはもちろん、 ポスターやチラシを独自につくって啓発している自治体はある。
A市民福祉部長:今後、国の動向や他市町の取組 などを注視しながら、適切に対応していく。
A教育次長:令和5年に国 から香り付き製品の使用に当たって周囲の方への配慮を訴える啓発資料の提供があり、市内小中学 校にはそう周知を図っている。今後、香害及び化学物質過敏症への 配慮を必要とする児童生徒が安心して学校生活を送る環境の確保は、重要であると考えており、国や社会情勢の動向を注視しながら適切に対応していく。
Q:香害や化学物質アレルギーについての相談件 数や状況について
A教育次長:相談件数は 報告義務がないので把握していない。対応に 苦慮しているケースはないものと認識。それぞれの状況に応じて、適時・適切に対応しているものと認識している。
Q:教 育委員会の所管じゃなくて学校に任せているという認識か?保護者も先生も子どもが香害だと気づかないことも あるかもしれないので、香害というアレルギーがあることを知らせること、知ることで行動が 変わるはず。教育委員会として文科省の理念(誰1人取り残さない教育は教育改革の理念)を踏まえて、再度その対応について。
A教育次長(金子昭人) もし 原因が給食着の柔軟剤使用であると断言・断定できるようでありましたら、(断言できなければ注意喚起もしないの?)保護者に使用の制限を 呼びかけることもできる。教職員や授業参観時の保護者にも、来 校時の配慮事項として呼びかけることも可能。保健調査票を含め、保護者や児童生徒や本人や保護者、からの申出・相談に対し、しっかりと受け止め、できる範囲で配慮するなど、丁寧に対応していく。(当たり前のことを言っているだけで、こんなことが丁寧な対応とは言わない!)
○山下の意見: 原因が香害ということが断定できればいいが、誰も断定できない。だから苦しんでいる。だから周囲の理解が必要で、それを教 育委員会として率先してやってほしい。
国から令和5年にポスターが示されたから「貼りました」と言っていたが、 私が学校回った限りでは、そのポスターの存在自体も知らないという学校が結構あった。香害の認識を改めていただきたい。
↓ポスター ↓国からの情報提供
- 1 / 1