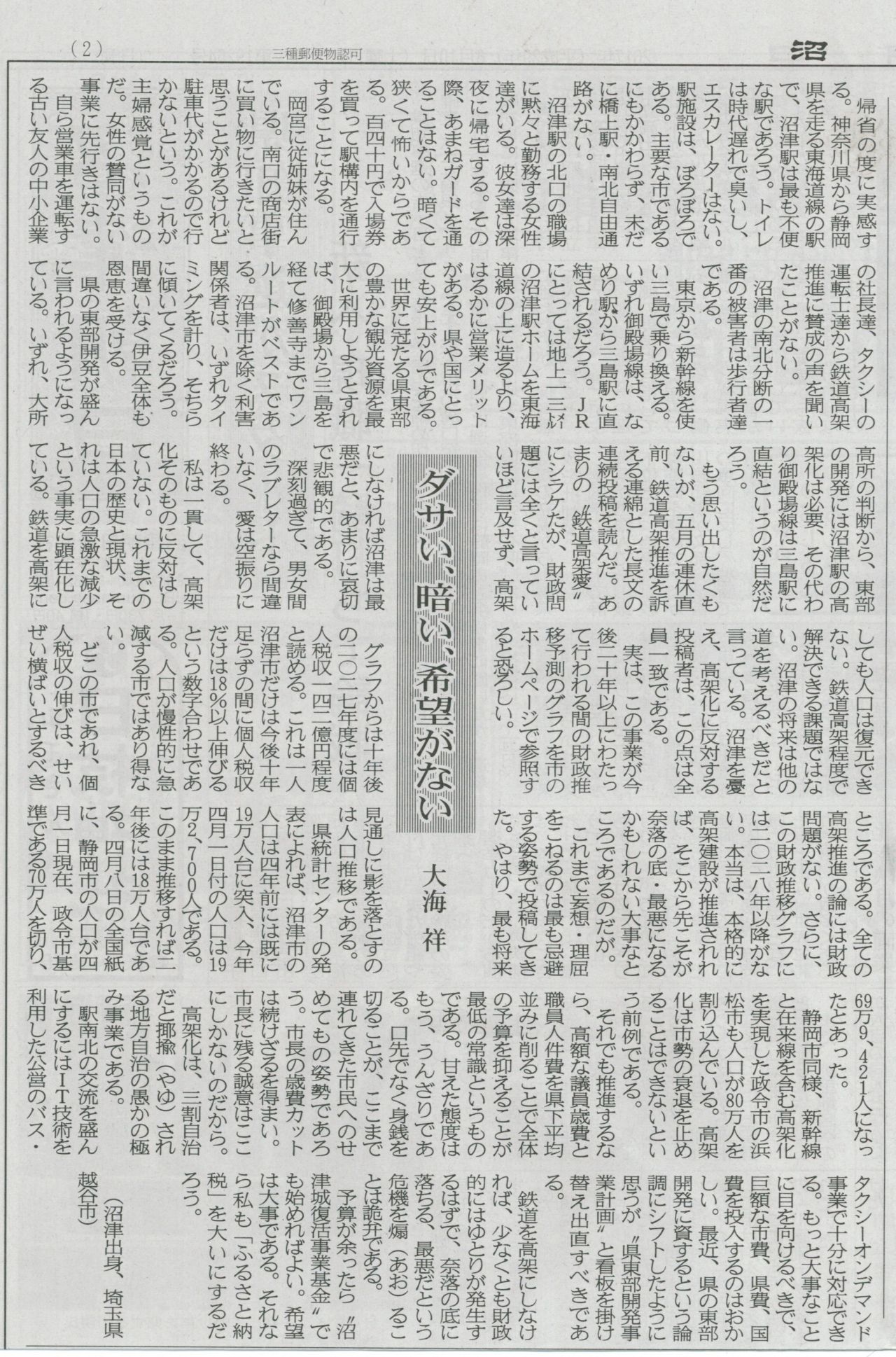山下ふみこオフィシャルブログ
2017.06.30
児童発達支援センターの担う機能
今日は3組の障害のある児童と保護者、そしてボランティアの方が市長と面会をした。
その一人は5歳のアズちゃんとママ。てんかんがあり、歩行不安定で移動手段はハイハイと歩行の両方。言葉を発することはなく、こちらの言葉の意味を理解することもできない。
その子たちは全員、「沼津市児童発達支援センターみゆき」に通っている。この施設は昭和49年にみゆき保育園として開設し、平成24年4月に未就学児の子どもたちの療育を行うセンターとしての役割を担っている。
その保護者と子どもが自分たちの通う「みゆき」の改善を求めて声をあげた。
”せめて他市の児童発達支援センターと同じレベルの支援体制に!”
(1)保育士の体制を3:1へ
特に肢体不自由児の場合、在籍児童3:保育士1:看護師1を徹底してほしい。
(2)肢体不自由児と他の障害児のクラスは完全分離へ
(3)PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)の必要性
(4)苦情解決について適切な対応を
ここまで来るにはいろいろの障壁があった。圧力や誤解、誹謗中傷もあったが、何よりも当事者たちが声を上げなければ、障害児に対する理解は変わらないと強く思ったことが今回の市長との面会につながった。
現場の改善は保育士の努力だけでは到底できないことである。アズちゃんのママは改善を求めて子育て支援課とも話した経緯があるが、今回、児童発達支援センターみゆきの意義と公立の果たす役割とはどうあるべきなのか、そんな疑問と思いを率直に市長にぶつけた。
市長は面会の当日、みゆきを訪れ子どもたちの様子を見に行ってくれていた。


7/1静岡新聞に昨日の市長訪問が掲載された。(記事をクリック→拡大)
障害者権利条約は2006年12/13に国連総会で採択された。日本の批准は2014年1月に国連で承認されている。その条約の第7条に”障害のある子ども”として
「政府は、障害のある子どもが、ほかの子どもと同じく、すべての人権と自由がもたらす利益を受けられるように、ありとあらゆる可能な行動をとることを約束します。また、障害がある子どもが、自分に影響があるすべてのことについて、必ず自分の意見を自由に言えるようにすることも約束します。それぞれの子どもにとって一番良いことを、いつでもまず、考えなければなりません。」国は、この権利を実現するために、障害がある子どもに必要な情報を与え、支援しなければならない。
Nothing about us whithout us !
(私たちのことを、私たち抜きで勝手に決めないで!)
良かれと思って大人たちが決めたことが、実は当事者たちにとってとても負担が大きかったりするもの。今回このような要望をした保護者たちは組織や団体に所属しているわけでもなく、ふつうのお母さんたちである。
その当事者たち自らが声を上げることはまだまだ厳しい現実の中で、わが子に関わる問題に主体的に関与し、改善を求めようとしたことはとても意義があり、勇気のいることだと思う。
市長との面談の冒頭に母親の一人が言った、「批判をしに来たのではない、理解を求めに来たのです。それは私たちや現場の努力では変えられない、だから市長へお願いに来たのです・・」
その心からの叫びに少しでも耳を傾けていただけますように。
2017.06.19
知事選の争点ならず鉄道高架は県事業
今朝の朝日新聞に、今回の県知事選挙において、県事業である鉄道高架事業は全く争点にならず、2人の候補者は推進の立場をとる。
今から30年前に市長も議会も高架化方針を出し、2006年(H18)に事業認可を受け、これから20年~30年かけて高架化事業を進めていくという予算規模も工期も完成時期も県事業として壮大な事業であり、長期になればなるほど、その完成時期の不確定要素は高まっていく。
一自治体の沼津市にとっては今までかつて経験したことのない超巨大な公共事業であり、自治体として生命をかけていると言っても過言ではない。(↓記事クリック拡大)
しかし、生命をかけるに値するほど魅力のある事業ではないからなのか、住民の無関心さはさらに他人事のようになりつつある。
一見何事もないように過ぎている日常生活の中で、財政的には徐々にこの町をむしばんでいる。子育て世代の危機感は人口流出という社会現象に歯止めがかからないというのもその表れだと私は思う。
0歳児の人口はこの10年間で30%も減少しているのはご存じだろうか。20年後に成人になる彼らにこの事業の責任はないが、確実にその借金返済は税の平準化というなかで、負担を背負う責務を否が応でも課される。だからこそ、逃げるが勝ちと思う親心が働く人口減の現象なのか・・・
2017.06.10
三島駅と御殿場線と駿豆線が直結したら?
今朝の沼津朝日新聞6/16に大海祥さん投稿の「いずれ御殿場線は納米里駅から三島駅に直結されるだろう・・・」という記事が目に入りました。
私の周辺でも、その声はずっと前から上がっています。
確かに御殿場線下土狩駅から三島駅までは近距離で1.5km、新たに線路を敷設するにしてもそう難しいことではないと思える。さらに三島駅から「いずっぱこ」に直結している。三島駅から修善寺駅を結ぶ伊豆箱根鉄道駿豆線を、私たちは昔から「いずっぱこ」と呼んでいるが、民家の軒先をすり抜けて電車が走る魅力的なローカル線。
費用対効果からいっても、沼津駅鉄道高架化のB/C(費用対効果)1.24より、はるかに大きな効果が広域的に受けられるだろう。どうせ、国からの補助金が半分400億円余こないとできない沼津鉄道高架事業なら、
国は沿線沿いの御殿場市、裾野市、三島市、長泉町、函南町、伊豆の国市、伊豆市と5市2町の広域プロジェクトとしてその費用対効果を検証してみたらどうだろうか?
何なら広小路駅の踏切を高架化にしたほうがさらに利便性は高まるだろう。(↓記事クリック拡大)
沼津市を4.2kmにわたって鉄道高架にする県事業ならば、5市2町の首長さんが団結すれば、広域的な街づ
くり構想が、県事業として展開するような気がする。
かつては「大きいことはいいことだ!」といって、どのまちも高度経済成長時に道路を拡張し、人口増加とともに学校を始めとした公共施設をつくってきた。
しかし、いま地域創生と言って元気な街の様子をみると、かつての高度成長期に乗り遅れたような処、つまり、合併もせず、再開発事業にも手を出さなかった道幅もほどほどの裏通りや路地のあるちょうど三島のような「コンパクトなまち」が見直されている。
そんなまちの路地裏を歩くと、各軒先はきれいに掃き清められていてお花が植えられている。その家の住人の小さな思いが伝わってくる。ちょうど小布施のような街並みだなぁと思う。
もしかしたら、すでに水面下で5市2町の構想があるかもしれない。沼津市に遠慮して、言い出せないってことはないのになぁ~
同じ税金を使うなら、まずは5市2町さんいかがでしょうか?もしかしたら、それが沼津市民をすくうことにも繋がっていくのだと思います。
始まった県知事選挙にこんな構想をぶつけたら、どちらも似たり寄ったりの争点がない、夢がない県知事選挙が一挙にクローズアップされると思うけどなぁ~